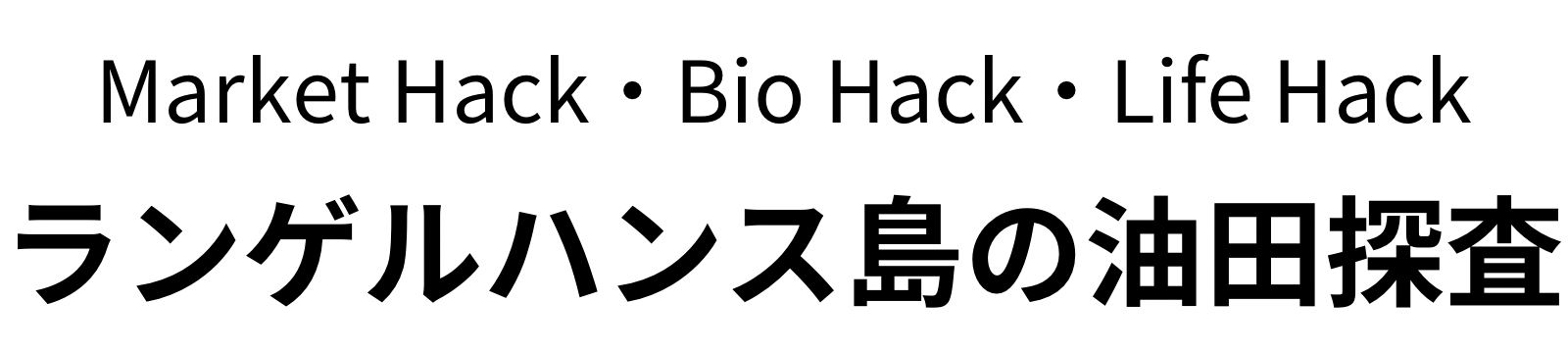以前にメラトニンは年配者の不眠に効果的という記事を書いた訳ですが、今回はメラトニンの安全性について調べた論文がありましたので共有します。(R)
ということでさっそく見ていきましょう。
論文の背景と目的
不眠症は多くの人が抱える悩みであり、特に高齢者においてその頻度は高くなります。不眠症は、寝つきが悪い、夜中に何度も目が覚める、朝早く起きすぎる、眠った感じがしないといった症状が続き、日中の生活に支障をきたす状態です。
メラトニンは人間の脳内(松果体)から夜間に分泌されるホルモンで、体内時計を調節し、睡眠を促す働きがあります。加齢とともにこのメラトニンの分泌は減少することが知られており、特に高齢者の不眠との関連が注目されています。
ヨーロッパなどでは、持続放出型メラトニン(PRM:Prolonged-Release Melatonin)が高齢者の不眠に対する短期的な治療薬として使用されており、その効果と安全性はある程度確認されています。
しかしこの論文で焦点が当てられているのは、次の3つの疑問です
- 高齢であることと体内のメラトニン量の少なさのどちらが、PRMの効果に関係しているか?
- 持続放出型メラトニンの効果は短期間だけでなく、長期間(6か月)にわたって持続するのか?
- 長期間使っても安全か? 副作用や依存性はないか?
実験概要
対象者
- 18~80歳の成人で、原発性不眠症(他の病気によるものではない不眠症)と診断された患者
- 入眠までの時間(睡眠潜時)が20分以上ある人
- 合計:930人が登録され、791人がランダム化試験に進み、最終的に722人が解析対象となった
試験デザイン(33週間)
1. 2週間:プラセボ投与(導入期間)
2. 3週間:持続放出型メラトニンまたはプラセボ(第一ランダム化)
3. 26週間:持続放出型メラトニン継続 or プラセボ再割り当て(第二ランダム化)
4. 2週間:全員プラセボ(離脱影響の確認)
という合計33週間の
- 使用薬:PRM(Circadin® 2mg)を毎晩、就寝2時間前に1錠服用
- 評価指標(主に患者の記録による)
- 主評価項目:睡眠潜時(入眠までにかかる時間)
- 副次項目:総睡眠時間、睡眠維持、睡眠の質、朝の目覚めの感覚、日中の活力、生活の質など
- 安全性は、副作用、バイタルサイン(血圧・脈拍など)、ホルモン値などで評価
明らかになったこと
65歳以上の患者では持続放出型メラトニンが明確に効果を発揮
- 寝つきにかかる時間が平均で15.6分短縮(PRM群 -19.1分 vs プラセボ群 -1.7分)
- 睡眠の質や朝の目覚めの良さも改善
- 総睡眠時間もやや延長し、朝の活動のしやすさにも好影響が見られた
- 効果は3週間だけでなく、6か月間継続して使用しても維持され、耐性(効かなくなること)は確認されなかった
若年層(18~64歳)でメラトニンが少ない人には明確な効果は見られなかった
- メラトニンの尿中代謝物(6-SMT)が8μg/夜以下という「低メラトニン群」でも、PRMとプラセボの間に有意差はなかった
- つまり、「若くてもメラトニンが少ない人=PRMが効く」という単純な図式ではなかった
副作用は軽微で、安全性に問題なし
- 鼻風邪、関節痛、軽度の消化不良、頭痛などが最も多い副作用
- PRM群とプラセボ群で副作用の出現率に大きな差はなし
- 血圧・心電図・ホルモン値にも異常なし
- 依存性・離脱症状(薬を急にやめたときの反応)も認められなかった
不明確な点・判明しなかったこと
若年層での有効性はまだはっきりしない
- 高齢者では明確な効果が確認されたが、若年者ではメラトニンの量だけでは効果が予測できなかった
- 若年層でのPRMの有効性については、さらなる研究が必要
「メラトニンが少ない人」がなぜ効果を感じにくかったのか?
- 単純に体内のメラトニン量が少ないからといって、それがすぐに不眠の原因になるとは限らない
- 「個人のメラトニンの年齢による低下幅」や「脳の感受性」のような、もっと複雑な要素が関与している可能性がある
(要は色々と考えられる要因は思いつくけど、よく分からんという事ですね。個人的にはメラトニン受容体とか作用してそうと思うところですけど、どうなんでしょうかね。)
他の安全性についての論文はどうか
- 44人の子ども(平均6才)に1日5mgのメラトニンを飲んでもらった研究でも、3.8年が過ぎても何の副作用も起きなかった(R)
- 1回あたり500mgの大容量のメラトニンを使った実験(R)でも、 特に問題が起きていない。
- 500mgのメラトニンを静脈注射した実験(R)でも何も起きていない。
というわけで、 長期の試験でも、 大用量の試験でも、 これといった問題は起きていないようです。 そう考えると、 わりと安全性が高い サプリと言えるんじゃないでしょうか。n=1ではありますが、個人的にもメラトニンを6mg定期的に摂っておりますがこれと言って副作用は確認していません。
メラトニンの副作用はどんなものがあるのか
ここまで安全性を語ってきましたが、どんなサプリにも副作用があるものです。メラトニンとてすべての人に適しているわけではありません。 一部の研究では、 こんな副作用が報告されております。
- 頭痛:メラトニンの副作用としては、最もよく報告されやすいものの一つ。
- 日中の眠気: メラトニンの睡眠促進作用は日中も続き、日中に疲れを感じることがある。特に高齢者の場合は、メラトニンを体内で処理する時間が長くなるため、翌日に眠気が起きやすい。
- めまい: めまいも報告件数が多い副作用であり、メラトニンのサプリメントを摂取する際は、アルコールの使用を避けるのが重要。
- 吐き気: メラトニンを飲むタイミングによっては、サプリメント摂取時に吐き気が起こることがある。
- 鮮明な夢や悪夢: メラトニンを使用している人は、しばしば鮮明な夢や悪夢を報告する。
- 胃痙攣: いくつかの研究では、メラトニンの使用によって胃痙攣や不快感が起こると報告されている。
- 気分の変化:短時間の抑うつやイライラなどが起きることがある。
いずれも重度の問題ではないものの、これらの副作用が起きるときは、メラトニンの使用を中止する必要があるでしょう。
また、当たり前ですが、以下のような人もメラトニンで問題が起きやすいので注意です。
- 透析を受けている人や肝臓に問題のある人: 腎臓や肝臓の機能が低下している人は、メラトニンを代謝できない可能性がある。
- 妊娠中または授乳中の人: 妊娠中や授乳中の人に対するメラトニンの安全性を保証する証拠はない。
- 認知症の高齢者:メラトニンを代謝する能力が下がり、 脳に影響を与える可能性がある。
- 精神疾患のある人: メラトニンは、人によってはうつ病やその他の気分障害の症状を引き起こすので。
- 免疫に問題のある人: メラトニンは免疫系の一部を活性化する可能性がある。この影響の重要性はまだよくわからないんだけど、 免疫系に問題がある人は飲むべきではない
これらの人々には、メラトニンのリスクがメリットを上回っちゃう可能性がありますので、くれぐれもご注意を。
まとめ
メラトニンの安全性について
- 65歳以上の高齢者に対するPRM(持続放出型メラトニン)の睡眠改善効果は明確であり、6か月間の長期使用も安全であった
- 年齢が治療効果の重要な指標であり、体内のメラトニン量だけでは効果を予測できない
- 副作用は軽微で、依存や離脱症状もなく、安全性が高い
- 44人の子ども(平均6才)に1日5mgのメラトニンを飲んでもらった研究でも、3.8年が過ぎても何の副作用も起きなかった
- 1回あたり500mgの大容量のメラトニンを使った実験でも、 特に問題が起きていない
- 500mgのメラトニンを静脈注射した実験でも何も起きていない
メラトニンの有効性と安全性を、長期間にわたって検証したものを含めて複数の論文で安全性が確認されております。ここまで確認された結果があれば、現実解として選択してもよろしいかと。
以前も言及しましたが、個人的に飲んでいるメラトニンサプリのリンクを貼っておきます。