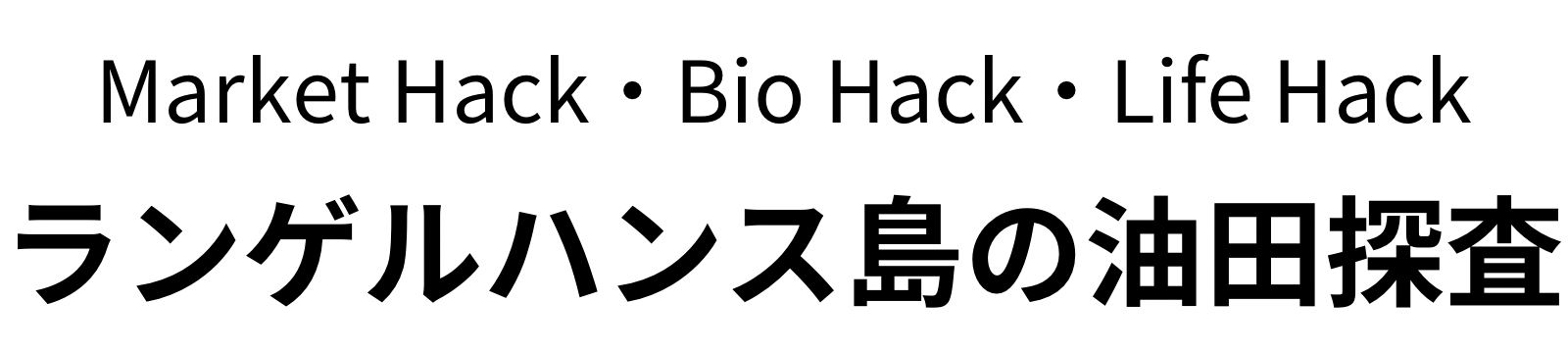最近は特茶などのペットボトルのお茶などにも含まれているケルセチンですが、具体的な効果を知っている人は少ないと思います。今回はポリフェノールの一種であるケルセチンの健康効果について、過去10~12年間の論文を基にまとめた医学論文があったのでまとめてみました。(R)
ケルセチンとは?
ケルセチンは、タマネギやリンゴ、緑茶、ブロッコリーなどの食品に含まれるポリフェノールの一種です。この成分は、植物が外的ストレス(紫外線や害虫など)から身を守るために作り出しているものですが、人間にとっても多くの健康効果があります。ケルセチンは、タマネギやリンゴ、緑茶などの食品に含まれる天然化合物であり、抗酸化作用・抗炎症作用・神経保護作用・抗がん作用などが報告されています。特に、加齢関連疾患(神経変性疾患、糖尿病、がん、心血管疾患)との関連が詳しくホットな話題となっています。
研究の概要
この論文では、ポリフェノールの一種であるケルセチンが加齢関連疾患(神経変性疾患、糖尿病、がん、炎症)に対して持つ健康効果を過去10~12年間の医学論文を基にまとめています。ケルセチンは強力な抗酸化作用、抗炎症作用、抗がん作用を持ち、様々な疾患の予防と治療に有望であることが示されています。本論文では、動物実験(in vivo)および細胞実験(in vitro)を用いた研究が紹介されており、以下の点が焦点となっています。
- ケルセチンが活性酸素を除去し、細胞の酸化ダメージを防ぐか
- 神経変性疾患(アルツハイマー病など)にどのような影響を与えるか
- 糖尿病の血糖値コントロールにどのように関与するか
- がん細胞の増殖を抑制するか
- 炎症反応をどの程度抑えるか
という事で詳しく見ていきましょう。
強力な抗酸化作用と細胞保護
酸化ストレスは、老化や病気の原因となる体内の「サビ」のようなものです。ケルセチンは、活性酸素(フリーラジカル)を除去し、細胞を守る働きをします。このため、老化を遅らせる効果が期待されています。
ケルセチンの抗酸化作用の仕組み
ケルセチンは、活性酸素を中和し、酸化ストレスから細胞を守る働きを持っています。その主なメカニズムは以下の3つです。
活性酸素を直接除去する
- ケルセチンはフラボノイドの一種であり、化学構造に抗酸化作用を持つ部分(フェノール基)を含んでいます。
- このフェノール基が電子を供給し、活性酸素を安定化(無害化)することで、細胞の酸化ダメージを防ぎます。
抗酸化酵素の活性を高める
- ケルセチンは細胞内の抗酸化酵素(SOD、カタラーゼ、グルタチオンペルオキシダーゼ)の働きを促進する。
- これにより、体内の抗酸化システムが強化され、活性酸素の影響を受けにくくなる。
炎症を抑え、酸化ストレスの悪影響を防ぐ
- 活性酸素は炎症を引き起こす原因となるため、酸化ストレスが高まると、炎症性サイトカイン(IL-6、TNF-α)が増加する。
- ケルセチンは炎症を引き起こす物質の生成を抑え、細胞へのダメージを軽減する働きを持つ。
実験概要
- 酸化ストレスの指標(MDAレベル)と抗酸化酵素(GSH、SOD)の活性を測定
- ヒト赤血球(RBC)を用いた実験で、ケルセチン投与後の酸化ダメージの変化を評価
- 動物実験(マウス)での酸化ストレス軽減効果の確認
実験結果
- ケルセチン投与により、酸化ストレスの指標であるMDA(マロンジアルデヒド)のレベルが低下
- 抗酸化酵素(GSH、SOD)の活性が増加し、細胞の酸化ダメージが軽減
- ケルセチンは活性酸素を除去し、酸化ストレスを減らす効果があることが示唆された
神経を守り、認知症予防に役立つ
ケルセチンは血液脳関門(BBB)を通過する事が確認されており、アルツハイマー病の原因とされる異常なタンパク質(βアミロイド)の蓄積を減らすことが示されています。(血液脳関門を通過出来る物質は全体を通してみても少なく、認知症の薬を開発する上での一つの難しい課題としても知られています。血液脳関門は脳が自身を守る為に獲得した一つの保護なんですね。)さらに、脳の炎症を抑える作用もあるため、記憶力の低下を防ぐ可能性があります。
ケルセチンが神経を守るメカニズム
酸化ストレスから神経細胞を守る
- 脳は活性酸素の影響を受けやすく、酸化ストレスによるダメージを受けると神経細胞が死滅する。
- ケルセチンは、活性酸素を除去することで、神経細胞を酸化ダメージから保護する。
神経炎症を抑える
- 脳内で炎症が起こると、神経細胞の機能が低下し、アルツハイマー病の進行が早まる。
- ケルセチンは、炎症を引き起こす物質(IL-6、TNF-α)の分泌を抑え、神経細胞を守る。
βアミロイドの蓄積を防ぐ
- アルツハイマー病の原因となる異常タンパク質(βアミロイド)の蓄積が、神経細胞を破壊する。
- ケルセチンは、βアミロイドの蓄積を減らし、アルツハイマー病の進行を抑える。
神経細胞の成長を促進
- ケルセチンは、脳内の神経細胞の成長を助ける因子(BDNF)の分泌を促進する。
- これにより、ダメージを受けた神経の修復が促され、記憶力の低下を防ぐ。
ケルセチンの神経保護効果を示した実験
アルツハイマー病モデルマウスを用いた実験
実験内容
- アルツハイマー病モデルマウスにケルセチンを投与し、記憶力やβアミロイドの蓄積を評価。
実験結果
- ケルセチン投与群では、脳内のβアミロイドの蓄積が減少。
- 記憶力テスト(迷路テスト)で成績が向上し、学習能力が改善。
神経細胞を用いた細胞実験
実験内容
- 酸化ストレスを与えた神経細胞にケルセチンを加え、細胞の生存率を測定。
実験結果
- ケルセチンを投与した細胞は、酸化ストレスによる細胞死が抑制された。
- 神経細胞の修復が促進され、細胞の寿命が延びた。
血糖値を下げ、糖尿病を予防
ケルセチンは、血糖値の上昇を抑え、インスリンの働きを助けることで糖尿病の予防や管理に役立ちます。研究によると、糖尿病モデルの動物にケルセチンを与えると、血糖値が改善し、膵臓のβ細胞(インスリンを作る細胞)の機能が維持されることが確認されています。
ケルセチンが血糖値を下げるメカニズム
インスリンの働きを改善(インスリン感受性の向上)
- 2型糖尿病では、インスリンが効きにくくなる(インスリン抵抗性)ため、血糖値が下がりにくい。
- ケルセチンは、インスリン受容体を活性化し、インスリンの働きを強化することで、血糖値を下げる。
膵臓のβ細胞を保護
- 膵臓のβ細胞は、インスリンを分泌する重要な細胞だが、酸化ストレスや炎症によって破壊されることがある。
- ケルセチンは、抗酸化作用と抗炎症作用により、膵臓のβ細胞を保護し、インスリン分泌の低下を防ぐ。
糖の吸収を抑える
- 小腸での糖の吸収を抑制することで、食後の血糖値の急上昇を防ぐ。
- 糖の分解を行う酵素(α-グルコシダーゼ、α-アミラーゼ)の働きを阻害し、ブドウ糖の吸収を遅らせる。
糖の消費を促進
- ケルセチンは、細胞のエネルギー代謝を活性化し、糖の消費を増やす。
- 特に、AMPK(AMP活性化プロテインキナーゼ)を活性化し、筋肉や肝臓での糖の取り込みを促進する。(AMPKは抗老化関連でも注目されており、糖尿病の第一選択薬であるメトホルミンもAMPKを活性化させて糖尿病にアプローチしています。)
ケルセチンの血糖値改善効果を示した実験
糖尿病モデルマウスを用いた実験
実験内容
- 糖尿病モデルマウスにケルセチンを投与し、血糖値やインスリン分泌量を測定。
実験結果
- 血糖値が有意に低下し、インスリン感受性が改善。
- 膵臓のβ細胞の損傷が減少し、インスリン分泌能力が維持された。
ヒトの細胞を用いた細胞実験
実験内容
- ヒトの膵臓β細胞にケルセチンを加え、酸化ストレスによるダメージを測定。
実験結果
- ケルセチンを投与した細胞は、酸化ストレスによる損傷が大幅に軽減。
- β細胞の機能が維持され、インスリン分泌量が増加。
がん細胞の増殖を抑える
ケルセチンは、がん細胞の増殖を抑え、細胞の自然死(アポトーシス)を促す作用を持っています。特に、大腸がん、乳がん、前立腺がん、白血病などで有効性が示唆されています。ただし、がん治療として用いるにはさらなる研究が必要とのこと。
ケルセチンががん細胞の増殖を抑えるメカニズム
本論文では、ケルセチンが以下のような働きを通じて、がん細胞の増殖を抑制することが示されています。
がん細胞の増殖を抑制
- がん細胞は通常の細胞と異なり、増殖のスピードが速い。
- ケルセチンは、がん細胞の増殖に関与するシグナル伝達経路(PI3K/Akt、MAPK経路など)を阻害し、細胞分裂を遅らせる。
アポトーシス(細胞の自然死)を促進
- 正常な細胞にはアポトーシス(プログラムされた細胞死)の仕組みがあり、不要な細胞は自然に死滅する。
- がん細胞はこのアポトーシスを抑制し、無限に増殖するが、ケルセチンはアポトーシスを再活性化し、がん細胞の自滅を促す。
血管新生を阻害
- がん細胞は新しい血管を作り、栄養を独占することで増殖する。
- ケルセチンは、血管新生を促す因子(VEGF)の働きを抑え、がん細胞への栄養供給を阻害する。
抗酸化作用によるDNA損傷の防止
- 酸化ストレスによってDNAが損傷すると、がん細胞が発生しやすくなる。
- ケルセチンは、活性酸素を除去し、遺伝子の損傷を防ぐことで、がんの発生を抑制する。
ケルセチンのがん抑制効果を示した実験
大腸がん細胞を用いた細胞実験
実験内容
- 大腸がん細胞にケルセチンを投与し、細胞の増殖率やアポトーシスの誘導を測定。
実験結果
- ケルセチンを投与したがん細胞は、増殖速度が低下。
- アポトーシス(細胞死)が活性化され、がん細胞の数が減少。
乳がんモデルマウスを用いた動物実験
実験内容
- 乳がんモデルのマウスにケルセチンを投与し、腫瘍の大きさや転移の進行を評価。
実験結果
- ケルセチン投与群では、腫瘍の増殖が抑えられ、転移の進行が遅延。
- がん細胞の血管新生が抑制され、栄養供給が減少。
勘違いしないでほしいのはケルセチンだけで癌が消えるという事ではない事。あくまで、癌の予防のサポートとして使えるかもということ。
炎症を抑え、慢性疾患を予防
ケルセチンは、炎症を引き起こす物質(サイトカインなど)の働きを抑えることで、関節炎や心血管疾患のリスクを減らす可能性があります。また、アレルギーの原因となるヒスタミンの放出を抑えるため、花粉症の症状緩和にも役立つとされています。
本論文では、ケルセチンがヒスタミンの放出を抑制するメカニズムについて以下の点が指摘されています。具体的に言えばケルセチンがヒスタミンを抑える仕組みとして以下のようなものがあります。
ケルセチンがヒスタミンを抑える仕組み
マスト細胞の安定化
- マスト細胞(肥満細胞)は、アレルギー反応時にヒスタミンを放出する主要な細胞。
- ケルセチンは、マスト細胞の細胞膜を強化し、ヒスタミンの放出を抑える。
- これにより、花粉症や蕁麻疹の症状が軽減される。
ヒスタミン産生を抑える
- ヒスタミンはヒスチジン脱炭酸酵素(HDC)によって作られる。
- ケルセチンは、HDCの働きを阻害し、ヒスタミンの産生量を減らす。
炎症を引き起こすサイトカインの抑制
- IL-6、TNF-α、IL-1βなどの炎症性サイトカインは、ヒスタミンの放出を促進する。
- ケルセチンは、これらのサイトカインの分泌を減らし、ヒスタミンの過剰放出を防ぐ。
実験概要
動物実験(マウス)
- 炎症モデル動物にケルセチンを投与し、炎症マーカー(IL-6、TNF-α)の変化を測定
- 抗炎症作用を持つ遺伝子の発現レベルを評価
- 慢性炎症に関与する酵素(COX-2、NF-κB)の活性を調査
- アレルギー誘発マウスにケルセチンを投与し、ヒスタミンの分泌量を測定。
- マスト細胞の安定性や炎症性サイトカインの減少も評価。
実験結果
- ケルセチン投与後、炎症マーカー(IL-6、TNF-α)が減少
- COX-2やNF-κBの活性が低下し、炎症反応が抑制された
- ヒスタミンの放出量が顕著に減少。
- 炎症性サイトカイン(IL-6やTNF-α)も低下し、アレルギー反応が抑制された。
細胞実験(ヒトマスト細胞)
実験内容
- ヒトのマスト細胞にアレルゲンを加え、ケルセチンを投与。
- ヒスタミンの放出量を測定。
実験結果
- ケルセチン投与によりヒスタミンの放出が約50%低下。
脂質代謝を改善し、肥満予防に貢献
肥満マウスの研究では、ケルセチンを与えることで体重増加が抑えられ、脂肪の代謝が改善されることが確認されています。また、血中のコレステロールや中性脂肪を減少させる作用も報告されています。
本論文では、ケルセチンが以下の方法で脂質代謝を改善し、肥満を防ぐことが示唆されています。具体的にはケルセチンが脂質代謝を改善するメカニズムとして以下のようなものがあります。
ケルセチンが脂質代謝を改善するメカニズム
脂肪の分解を促進する(リパーゼの活性化)
- ケルセチンはホルモン感受性リパーゼ(HSL)を活性化し、脂肪の分解を促進する。
- これにより、脂肪細胞に蓄積した脂肪がエネルギーとして利用されやすくなる。
ミトコンドリアでの脂肪燃焼を促進する
- ケルセチンはミトコンドリアの機能を向上させ、脂肪の燃焼(β酸化)を促進する。
- これにより、脂肪が効率的にエネルギーに変換され、肥満を防ぐ。
脂肪の合成を抑制する
- ケルセチンは脂肪合成酵素(FAS)の働きを抑え、脂肪が過剰に蓄積されるのを防ぐ。
- これにより、内臓脂肪の増加が抑えられ、脂肪肝の予防にもつながる。
炎症を抑制し、脂肪細胞の肥大化を防ぐ
- 肥満に伴う慢性的な炎症(脂肪組織の炎症)は、脂質代謝を悪化させる。
- ケルセチンは炎症性サイトカイン(IL-6やTNF-α)の分泌を抑え、脂肪細胞の異常な増加を防ぐ。
肥満マウスを用いた実験
実験内容
- 高脂肪食を与えたマウスにケルセチンを投与し、体重の変化や脂質代謝に関与する遺伝子の発現を調べた。
実験結果
- 体重増加が抑制され、内臓脂肪の蓄積が減少。
- 脂肪分解酵素(HSL)の活性が向上し、脂肪の燃焼が促進。
- 脂肪合成酵素(FAS)の発現が低下し、脂肪の蓄積が抑えられた。
ヒト脂肪細胞を用いた細胞実験
実験内容
- ヒト脂肪細胞にケルセチンを加え、脂肪の分解や燃焼に関与する酵素の発現を調べた。
実験結果
- 脂肪の燃焼を促進するAMPKの活性が上昇。
- 脂肪の蓄積を抑える遺伝子の発現が増加。
ケルセチンの摂取方法と注意点
ケルセチンを多く含む食品
- タマネギ(特に赤タマネギ)
- リンゴ
- 緑茶
- ブロッコリー
- ケール
- ベリー類(ブルーベリー、ブラックベリーなど)
- 赤ワイン (個人的にはアルコールは少量でも身体に良くない事が判明しているのでケルセチン摂取目的では無しかなぁ)
- カカオ(ダークチョコレート)
サプリメントでの摂取
ケルセチンサプリメントも販売されていますが、適切な摂取量は1日500mg~1000mgが推奨されています。ただし、過剰摂取は腎臓に負担をかける可能性があるため、長期間の使用には注意が必要です。要はケルセチンの摂取目標は現時点では不明だし、個人差があるよねということ。
副作用や注意点
- 高用量のケルセチンを長期間摂取すると、腎臓や肝臓に負担をかける可能性があります。(要は代謝するときに多すぎると負荷が掛かるよねという話。これは他のサプリメントやアスピリンのようなNSAIDsのような薬にも言える事ですね。)
- 抗凝固薬(ワルファリンなどの血液をサラサラにする薬)を服用している人は、ケルセチンの摂取によって出血リスクが高まる可能性があるため、医師に相談してください。(要は血がサラサラになり過ぎるという事)
まとめ
ケルセチンは、タマネギや緑茶、リンゴなどに含まれるポリフェノールの一種で、抗酸化作用・抗炎症作用・神経保護作用・抗がん作用・脂質代謝改善作用など、多くの健康効果を持つとされています。
抗酸化作用により、活性酸素を除去し、細胞の損傷を防ぐことで老化や生活習慣病を予防します。また、神経保護作用を持ち、アルツハイマー病の原因であるβアミロイドの蓄積を減らし、記憶力の低下を防ぐ可能性があります。
糖尿病に対しては、血糖値を下げ、インスリンの働きを改善し、膵臓のβ細胞を保護することで予防・管理に貢献します。さらに、脂質代謝を改善し、脂肪燃焼を促進することで肥満を防ぐ働きもあります。
がんに関しては、がん細胞の増殖を抑制し、アポトーシス(細胞死)を促進し、転移の進行を遅らせる効果が動物実験で示されています。さらに、ヒスタミンの放出を抑え、花粉症やアレルギー症状を軽減する作用も確認されています。
このように、ケルセチンは健康維持に重要な成分であり、食品からの摂取が推奨される成分の一つです。個人的には玉ねぎや冷凍ブルーベリーで摂取していきたいですね。たまに、不規則な生活になるので、そのような時にサプリメントに頼りたいと思います。
一応、iHerbのケルセチンのサプリメントのリンクだけ置いておきます。
あとがき
ここではケルセチンとケルセチン配糖体の違いについてまとめておきます。ケルセチン配糖体は特茶などのペットボトルのお茶飲料に含まれていて有名ですね。
ケルセチンとケルセチン配糖体の違い
ケルセチン配糖体とは?
ケルセチン配糖体は、ケルセチンに糖(グルコース、ラムノースなど)が結合した化合物のことを指します。食品中では、ケルセチンは主に配糖体の形で存在しており、特に「ルチン」や「イソクエルシトリン」といった形で含まれています。
ということで、上で示した通り、飲料でケルセチン配糖体が含まれている理由は水に溶けやすくしているからなんですね。対照的に、ケルセチンは水に溶けにくく、脂に溶けやすい性質(親油性)を持っています。そのため、脂質と一緒に摂ることで、腸内での溶解度が高まり、吸収率が向上します。クエルセチンは脂溶性のため、胆汁酸(脂質の消化を助ける成分)と混ざることで、腸での吸収がスムーズになります。 特に、オリーブオイルや魚の脂などの良質な脂質と一緒に摂ると、吸収が効率よく行われる可能性があります。
ケルセチンをサプリメントで摂る場合は炒め物などの油物と一緒に摂る事が大事そうです。